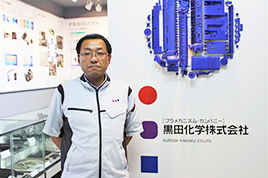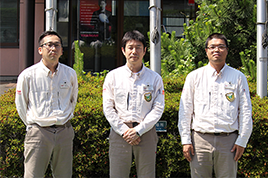-

- 西武信用金庫
KAITOセキュアカメラの導入で
担保物件の評価や現地調査に伴う
撮影業務にストレスなくあたれる環境を整備
撮影から内部環境へのデータの取り込み、
データ共有までのプロセスを安全かつ
効率的に運用することが可能に

目的
撮影から内部環境へのデータの取り込み、職員間でのデータ共有までのプロセスを効率化するとともに、情報漏えいリスクも極小化したい
- 概要
- 西武信用金庫(以下、西武信金)は、全職員に貸与するスマートフォンで担保物件評価のための現地調査での撮影業務を行えるスタイルを確立したいと考えた
- デジタルカメラを貸し出すスタイルには端末の盗難・紛失による情報漏えいリスクがあった
- 撮影後の内部環境へのデータの取り込み、職員間のデータ共有のプロセスが職員の利便性を損ねており、時間的・資源的ロスがあった
- KAITOセキュアカメラの導入により職員が自由に撮影業務にあたれるようになり、情報共有も迅速化した
- 課題
- デジタルカメラの盗難・紛失による情報漏えいリスクがあった
- 撮影データの内部環境への取り込みとデータ共有に非効率があり、職員の利便性を損ねていた。
- 選定理由
- 撮影された画像データがサーバへ転送されると、端末内のファイルが自動的に削除される
- セキュリティだけでなく、使い勝手や管理・運用面の機能、コストなどの要件もクリアした
- 導入の効果
- 職員はいつでも自由に撮影業務にあたれるようになった
- 撮影から内部環境へのデータの取り込み、職員間でのデータ共有までの一連のプロセスが円滑化し、情報漏えいリスクも低減した
- KAITOセキュアカメラの利用シーンは広がっており、当金庫ブログ(地域密着ストーリー)の制作にあたっても、地域の魅力が効果的に伝わるような瞬間を画像としてしっかりと記録できるようになった
撮影から情報共有までを
安全かつ効率的に行いたい
西武信金は、東京都全域と埼玉県、神奈川県の一部を主な営業地盤とする協同組織金融機関である。「人間主義」という基本理念のもと、預金業務や融資業務、為替業務に加え、さまざまな分野の外部専門家と連携して経営課題を解決するための支援業務などを展開している。SDGsや脱炭素経営に資する融資商品の開発や中小企業支援に力を入れていることも特長だ。
同信金は2020年11月にDX推進プロジェクトを発足し、特定のテーマや目的別に複数の分科会を設置。デジタル技術の活用を軸にさらなる業務効率化と顧客体験の向上を目指す中でリモートワークを支えるITインフラの整備に着手することになった。
人事部 副部長(元 経営企画部 副部長 DX推進事務局) 松本 聡氏は、「当時、コロナ禍によって非対面の生活様式が広がり、リモートワークとリアル出勤を組み合わせた働き方の再設計と顧客接点の強化が急務となっていました。その中でリモートワーク環境の実現に向けたプロジェクトが立ち上がり、全職員にスマートフォンを貸与することが決まりました。そこで顧客との連絡ルールや職員間の内線電話にとどまらない活用法として検討されたのがカメラアプリを利用した画像撮影だったのです」と語る。
たとえば、取引先融資における担保物件の評価や現地調査のシーンでは撮影が必須だ。そこで記録されたデータは融資事務職員などに共有され、融資審査や各種資料作成などに用いられるのが通例である。これまで同信金では職員にデジタルカメラを貸し出して撮影にあたらせてきたが、このやり方にはいくつかの問題があったという。
まずは、デジタルカメラの盗難・紛失によって機微な情報が漏えいしてしまうリスクがあったことだ。また、撮影者がデジタルカメラを借り受けるためには管理簿に必要事項を記入し、デバイス管理者の承認を得なければならなかった。煩雑な貸出申請プロセスが職員の利便性を損ねていたのだ。さらに、撮影後の内部環境へのデータの取り込み、職員間でのデータ共有のプロセスにも時間的・資源的ロスがあった。実際、撮影者は記録した画像をスタンドアロンのプリンターやコンビニのコピー機で紙に印刷した上でスキャナによるデータ化を行い、ファイルサーバの共有フォルダに収めなければならなかったのだ。
システム企画部 副部長 大寺 祐司氏は、「スマートフォンの標準カメラを使えるようにするとデータがスマートフォンに残ってしまうリスクがあった。何を撮影されるかわからず、万が一個人情報が写っていた場合、スマートフォン紛失時に個人情報の漏えいとなってしまう。スマートフォンの利用を前提として、撮影から情報共有までの一連のプロセスを安全かつ効率的に行えるツールが必要だったのです」と話す。

システム企画部 副部長 大寺 祐司 氏(右)
JMASのサポートにより短期間での導入を実現

西武信金は、撮影から情報共有までのプロセスの効率化と情報漏えい対策の強化を実現するツールの調査を開始。インターネットでの情報収集によって唯一探し当てたのがKAITOセキュアカメラだった。
システム企画部 調査役 指田 学氏は、「KAITOセキュアカメラは、カメラアプリとサーバ転送の仕組みで撮影データを端末内に残さない運用を強制し、迅速なデータ共有も実現できるツールの先駆け的存在です。管理・運用面の機能やコストの要件を満たすとともに、厳格なセキュリティ基準を設ける金融機関での導入実績もあったのですぐに評価してみることにしたのです」と語る。
その後、KAITOセキュアカメラについてDX推進プロジェクトメンバーに限定したトライアルを実施。主な機能や使い勝手に加え、撮影したデータが安全かつ確実にサーバに転送・格納されることなどを確認した。また、JMASとともに業務上の課題やニーズにもとづいた要件の洗い出し、仕様への落とし込み、撮影可能範囲や禁止事項などを含む運用ルールの策定も実施。JMASのサポートにより経営層や関連部署の意思決定に必要な内部資料を滞りなく準備でき、稟議から決裁までのフローを円滑に進めることができたという。
指田氏は、「JMASは運用面にかかる仕様変更や機能追加についても快く引き受けてくれました。KAITOセキュアカメラの検討開始から開発、導入までに要した期間は約3カ月と、われわれの予想を上回るスピードで要求どおりに仕上げていただけたことが印象的です。KAITOセキュアカメラを迅速にリリースできたのは、一斉導入してから間もなかったスマートフォンの利用促進の観点でも意味合いが大きかったですね」と話す。
撮影業務にかかる職員および運用者の
ストレスと負担を大幅に軽減
西武信金は2021年5月、担保物件の評価や現地調査に伴う撮影業務にKAITOセキュアカメラを利用できる環境を整えた。結果、職員はデジタルカメラの貸出申請プロセスを経ることなく、いつでも自由に撮影業務にあたることが可能に。機密管理を担う運用者側も撮影データに付与される個人コードや日時データを見れば、いつ、だれが、どこで、なにを撮影したかを把握できる体制だ。
撮影データの内部環境への取り込みと情報共有も迅速化した。実際、内部環境へのデータの取り込みは撮影後に転送ボタンをタップするだけで済む。そして、KAITOサーバ上に作成されたアルバムへアクセスすれば対象の画像データを閲覧、取得することが可能だ。
指田氏は、「カメラを持ち出していない外出中の職員でも、担保物件の現地調査のための撮影をいつでも行えるようになりました。撮影業務に伴う紙や印刷などの費用がなくなったのも成果の1つです」と語る。
KAITOセキュアカメラは、西武信金の写真撮影ツールとしてすっかり定着した。シンプルな操作で扱うことができ、パフォーマンスと安定稼働という点でもストレスフリーであることが大きな理由だ。
松本氏は、「地域情報や日々の取組みを発信する地域密着ストーリーというブログ制作にあたっても、地域の魅力が効果的に伝わるような瞬間を画像としてしっかりと記録しています。KAITOセキュアカメラは地域のみなさまと職員のコミュニケーションを促進するパイプとしても一役買っていると言えます。」と話した。
会社プロフィール

- 社名
- 西武信用金庫
- 本社
- 東京都中野区中野2-29-10
- URL
- https://www.shinkin.co.jp/seibu/
西武信金は、東京都全域と埼玉県、神奈川県の一部を主な営業地盤とする協同組織金融機関である。「人間主義」という基本理念のもと、預金業務や融資業務、為替業務に加え、さまざまな分野の外部専門家と連携して経営課題を解決するための支援業務などを展開している。SDGsや脱炭素経営に資する融資商品の開発や中小企業支援に力を入れていることも特長だ。